今日から試せる、「超・具体的」な声かけのコツ!
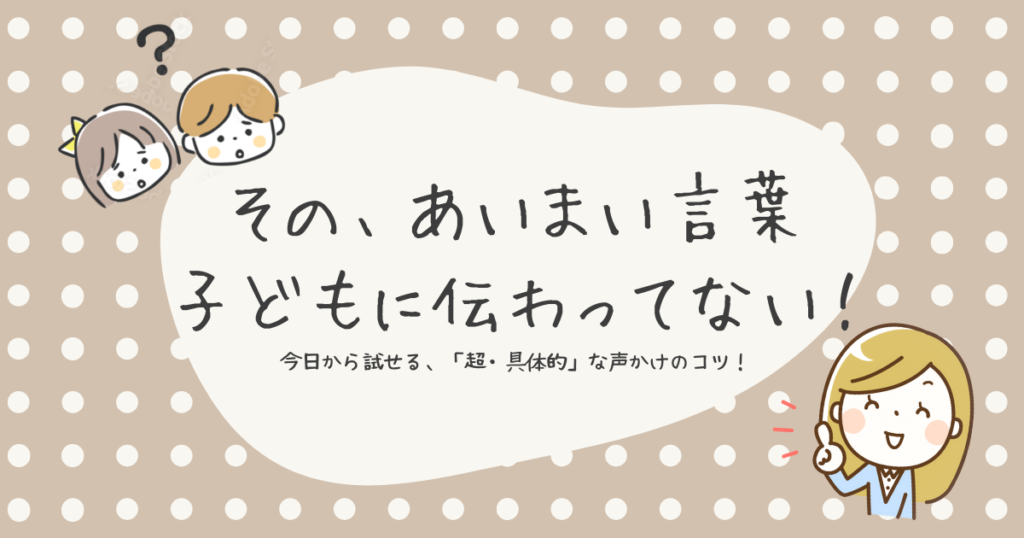
みなさんは、子どもに
「ちょっと待って」
「ちゃんとやって」
「きちんととして」と
注意することはありませんか?
この言葉は、
日常生活や学校生活で
よく使われる言葉ですが、
こんなアバウトであいまいな表現が、
イメージしにくくてピンと来ない子、
イマイチ伝わりにくい子は
案外多いんじゃないでしょうか
「ちょっと」や「ちゃんと」って、
目には見えません
この声かけを
「超・具体的」に変えるだけで、
どんな子にも伝わりやすくなると思います
そんな声かけが知りたい!と言う方は
最後までお読みください
「ちょっと」「もうすぐ」「だいたい」を具体的にしよう

あいまいな言葉を子どもに
伝わるようにするコツは、
「見えないものを具体的にイメージし、
それを相手と共有できるようにすること」
「時間」や「相手の気持ち」などは、
目には見えません
「適量」や「適度」などは、
その人によって感覚が違います
さらに「適切な行動」などになると、
その人の主観や価値観しだいでも
変わってくるのではないでしょうか
私としては使いやすく、
ついつい使ってしまいますが
経験の少ない小さな子どもや、
イメージすることが
苦手なタイプの子どもなどに、
「察して、推し量るべし」と
求めているようなものです
少々ハードルが高いと感じませんか?
子どもが経験を積むまでは、
こちらと同じイメージができるように、
数字・目安・行動などで
具体的に伝えることで、
分かってくれること、
実行できることも結構多いんです
ちょっと待って→あと〇分待って
例えば、家事をしている最中に
「早く、遊んで!」と
何度も子どもに急かされると、
「ちょっと待って」といいたくなりますが…
この「ちょっと」をあと
どれぐらいの時間なのかが分かるように、
「時計の長い針が
シールのところになったらね」
「あと3分待って」
「9時45分になったら、出かけよう」など、
具体的な数字を入れて伝えると
納得しやすくなります
最近はスマホのアプリに、
ゲージ付きのタイマーアプリや砂時計など、
「時間が見えるようになっているもの」を
一緒に使うと、より分かりやすいです
ハッキリとした時間が伝えにくい場合には、
「お母さんが、
この洗濯物をたたみ終わるまで待って」など、
具体的な行動などで区切りや目安を
伝えてあげると納得できることあります
我が家では、早く終わるように!と
息子たちがが一緒に
お手伝いしてくれることもあります
もうすぐだから→〇〇して待ってようか
子どもは、待つのが苦手なことが多いですよね
楽しみなことが目の前にあったら、
「ワクワクし過ぎて、待ちきれない!」のは
当然かもしれません
また、いつまで待てばいいのか
分からなくて不安になったり、
漠然と待っていると
どうしたらいいのか戸惑うこともあります
そんなときに、「もうすぐだから」と、
大人がうまいことお茶を濁そうとしても、
子どもは、
なかなか納得してくれないこともあります
例えば、新しく開店したばかりの
お店の長蛇の列に並んでいるときには、
「あと、〇人だよ」「今、◯番目だよ」など、
人数や回数などの具体的な数字を伝えて、
「ゴールが見える」ようにすると
安心できるかもしれません
このとき、整理券や番号札などがあると
分かりやすいですが、
お店で配ってない場合はもあります
そんな時は、メモ帳などに番号を
書いて渡してあげると、
落ち着けることもあります
小さな子には、指で見せてあげるだけでも
違うと思いますよ
また、「〇〇して待ってようか?」など、
具体的な待ち方を提案したり、
予めゲーム機やマンガなど、
好きなものを持参し、
待ち時間に「何をして待てばいいのか」が
ハッキリしていると、
結構気長に待てることもあります
そして、大人と子どもの時間感覚は違います
大人にとっては数週間後の話も
「もうすぐ」かもしれませんが、
子どもにとっては
とてつもなく先の話に感じられることも
あります
こんなときは、
一緒にカレンダーを
毎日斜線で消していったり、
メモ帳パッドで日めくりカウントダウンを
作ってあげたりするのもいいかもしれません
だいたいでOK→80%くらいできてればOK
例えば、子どもが宿題などで、
些細なことにこだわり、
今やっていることを終われないときに、
助け舟を出すつもりで
「だいだいでOK」なんて言っても、
真面目で完璧主義タイプの子などは
納得できないこともあるますよね
そんなときには、「だいたい」とは、
何%くらいのことなのか、
ひとまずの目安を具体的な数字で
伝えてあげるだけでも、
気持ちに区切りをつけやすくなります
ワークなどの課題に
1ページずつふせんを貼って
「今日は、ふせん◯枚取れれば大丈夫」とか、
優先順位をつけた一覧表を作って
「最低限ココまでできれば、十分だよ」など
ひとまずの合格ラインを引いてあげると、
安心できる子もいます
宿題などで、完璧さを求め過ぎて
なかなか終わらず、
子ども本人も悩んでいる場合などは、
あえて「字を雑に書く練習」をしてみたり、
「ココだけは完璧に」
「ココからは、“書いてあれば”OK」など、
一緒に「妥協ラインを引く練習」を
していくと、
子どもも少しラクになれるかもしれません
「ちゃんと」「しっかり」「キチンと」とは、行動に言い換えよう

「ちゃんと」「しっかり」「キチンと」などの
言葉も、その人それぞれの
主観や価値観次第で、
「どの程度が合格ラインなのか」が
変わってきます
どんなことをすれば「ちゃんと」になるのか、
「具体的な行動」をなかなか
明確にイメージできない子もいます
どんな行動をすればいいのか、
何ができていればいいのか、
こちらが想定している
「ちゃんと」の「中身」を
具体的に伝えると動きやすくなります
ちゃんとやって→〇〇君は、ここからここまで、片付けてくれる?
片付けの途中でウロウロしてしまう息子は、
「ちゃんと片付けして!」
なんて、しっかりもののお友達に
よく注意を受けます
みんなで何かをする場面で、
単独行動を取りがちな子や、
他人事のようにぼんやりしちゃう子などには、
「誰が、どこからどこまで、
何をやればいいのか」
その子の担当する範囲や役割を
明確にして、具体的な行動で
「個別に」お願いすると、
求めている行動を
実施してくれるかもしれません
とはいえ、ここまで子ども同士に
期待するのはハードルが高いので、
まずは、周りの大人が声かけの
お手本を見せることも大切です
大人が目の前で繰り返し声かけの
お手本を見せていると、
自然と子ども達がマネしてくれること、
いつの間にか身につけてくれることも多いです
しっかりやって→今やることを確認しようか?
大人が子どもに対して
「しっかりしている」と感じるとき、
子どもが自分で判断して
「自分が何をしたらいいのか分かり、
それを実行できている」ことが
多いのではないでしょうか
子どもに“しっかり”やって欲しいときには、
「今やること」「次にやること」
「何と何ができればいいか」などを
確認できる声かけなどをすると、
やるべきことを理解して実行でと思います
このとき、一緒に「やることリスト」に
書き出したり、計画表を作ったり、
ふせんなどを使って物事の
優先順位づけをしたりと工夫し
頭の中の整理整頓ができるようにすると、
先のことを見通して動くことが苦手な子でも、
実行力がUPします
最初は大人の声かけで促されいても、
「目標クリアできた」経験を積んでいくと、
次第に自分で判断して
できるようになっていきます
キチンとして→シャツをしまって、背筋を伸ばしてごらん
例えば、子どもの服装や姿勢を
だらしないと感じたとき
「キチンとして」と、注意したとしても…
その場に合った適切な服装や行動が
できないこともあります
それは、子ども本人が、
周りからどう見られるのかを
あんまり意識していないのかもしれません
その子に悪気はなく、
単に知らない・気づいていないだけのことも
多いので、
「どういった服装や行動をすれば、
キチンと見えるのか」を、
具体的に伝えればOK!
その際、写真・動画や、
大人や周囲の人の「実例」を見せるのも、
分かりやすくていいと思います
また、既に「キチンとする」とは、
どうしたらいいのかは(知識として)
知っているけど、
今がそのタイミングだと
気づいてないこともあります
この場合は、
「周りの人の服装を見てごらん」
「ここでは、どうすればいいと思う?」など、
周りに気づかせたり、
適切な行動を思い出せる声かけを
したりすると、
気づいて行動できるかもしれません
できるようになってきたら、あいまい言葉にも慣れていきましょう

子どもの周りの人達みんながいつも、
親切に丁寧に言ってくれるわけでは
ありません
なので、「超・具体的」な声かけで、
子どもが「どうしたらいいのか」
だんだん分かってきたら
あえて「ちょっと」「だいたい」「ちゃんと」
などを使ってみて、
あいまいな言葉の表現にも、
徐々に慣らしていくと良いです
だいたいでOK→そうそう、それくらいが“だいたい”
曖昧な表現で伝えて、実際にそれを
実行できたら、
「そうそう、それくらいが“だいたい”」と
フィードバックしたり、
うまくできなかったら、
「もう“ちょっと”こうしてくれる?」など
微調整して、
あいまいな言葉のイメージを
子どもと共有できるようにすると
調整する経験を積めます
こうして、少しずつ手を離していくことで、
少々イメージするのが苦手でも、
だんだん、具体的に言い換えるサポートが
なくても大丈夫になっていくと思います
お子さんの特性への理解を深めたい、
特性へのアプローチ方法を
見つけたいという方は、
ばらの公式LINEよりご相談ください
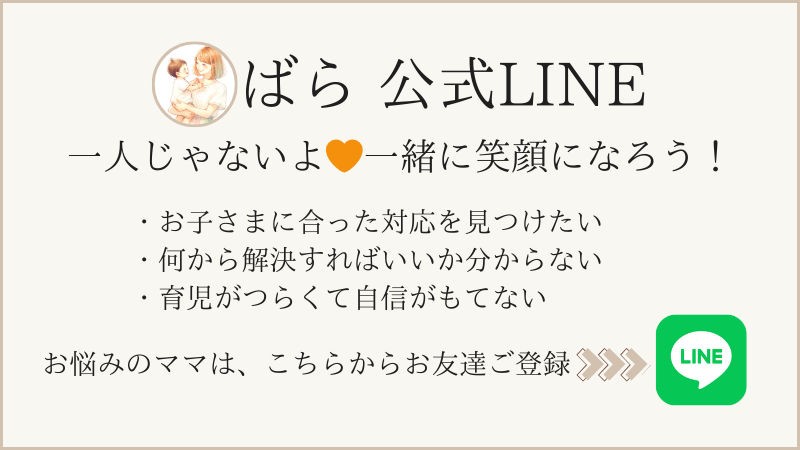
それではまた、お会いしましょう!
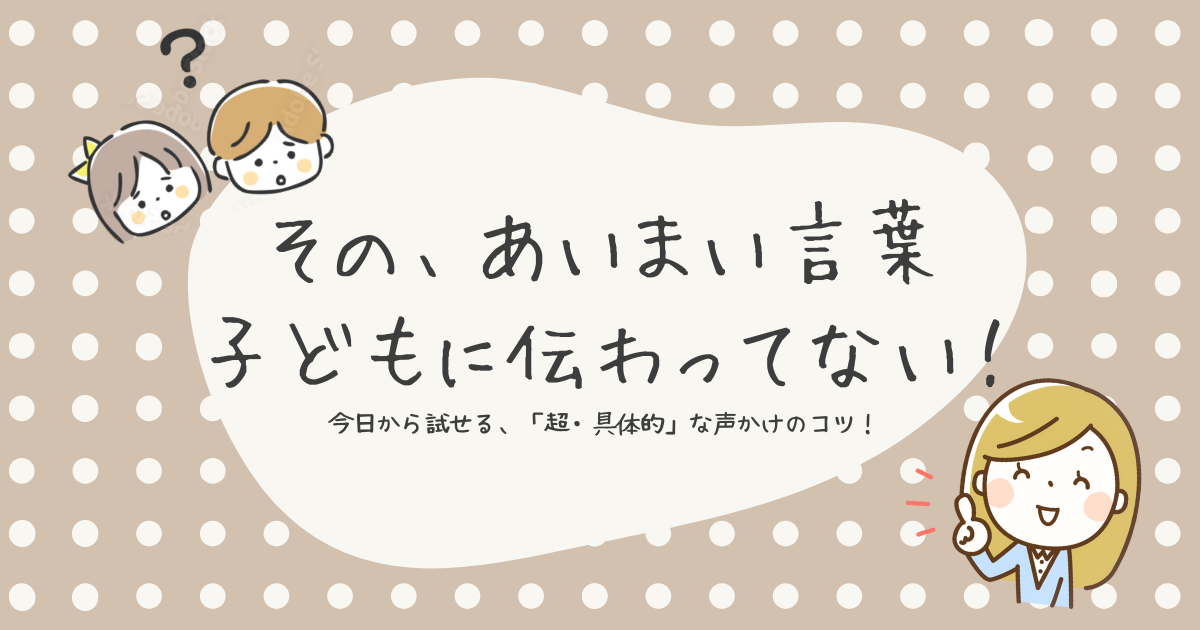
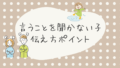
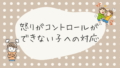
コメント